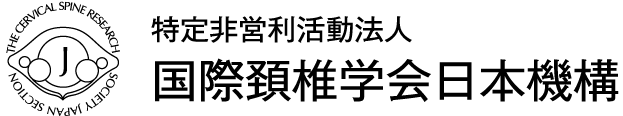カンボジア交流事業のご報告
2025年3月6日-7日にカンボジア・プノンペンにて頚椎領域の手術支援ならびに教育研修講演(セミナー)、手術手技ワークショップを行って参りましたのでご報告致します。 カンボジアとの交流事業は国際頚椎学会日本機構アジアパシフィック交流委員会が継続して行ってきた事業の一つです。COVID-19流行の影響で直接の現地に赴いての交流・支援が2019年以降中断しておりましたが、昨年5年ぶりに現地訪問が再開され、本年も無事に継続することができました。本年は湯川泰紹先生 (名古屋共立病院脊椎脊髄外科センター長)、宮本裕史先生 (神戸労災病院整形外科部長)、青山剛先生 (手稲渓仁会病院整形外科副部長)、北村和也 (防衛医科大学校整形外科学講座講師)の4名で訪問し (図1)、手術支援、セミナー開催、手術手技ワークショップの3つを計画、遂行して参りました。

初日の3月6日は午前中にKhmer-Soviet Friendship Hospitalを訪問しました。この病院では脳神経外科が中心に脊椎手術を行っておりました。医局の壁にはASIAの脊髄損傷worksheet (ISNCSCI)やAO Spineの頚椎外傷分類のポスターが貼ってあり、日常診療で外傷が占める割合が高いことが伺い知れました。当日は46歳男性のC3/4高位に生じた非骨傷性頚髄損傷に対する前方除圧固定術(ACDF)が予定されており、宮本先生と北村が助手を務め、手術は無事に執り行われました。皮切のデザイン、術野が先細りにならないような展開、無除圧固定術(ケージ挿入術)にならないための除圧操作など、我々が普段心がけているstep by stepを短い時間の中で伝えられるよう努めました。インプラントは中国メーカーのプレートとスクリューが常備されていましたがいずれもサイズは限定されており、また椎体間ケージも普段使うことが滅多になさそうな高さの(高い)ケージしかありませんでした。発育性脊柱管狭窄症および後縦靭帯骨化症のため広範囲でtight canalになっていたため、我々の第一印象は予防的除圧を含めた多椎間後方除圧でしたが、カンボジアでは特に脳外科の先生方は後方除圧よりも前方除圧に慣れておられるようでした。願わくば術前の準備段階から診断、手術計画を一緒に議論する時間があると、手術手技だけでなく治療方針決定に至る思考過程を共有でき、より有意義になるのではないかと感じました。
隣の手術室では腰椎椎間板ヘルニアに対する内視鏡下手術(Unilateral Biportal Endoscopy)が行われていました。昨年の報告書にもありました通り、日本で研修を積んだ医師らは内視鏡技術に磨きをかけ、総合病院での診療に加え、プライベートクリニックで低侵襲手術を提供しております。日本と同様ですが、新技術の導入が進む一方で、特に頚椎領域においては病態の理解と、治療方針決定における考察をより深めていく努力が継続して必要と感じました。

午後にはCambodia-China Friendship Preah Kossamak Hospitalに移動しました。22歳男性に生じたC4/5片側椎間関節脱臼による脊髄損傷に対する手術が予定されていました。カンボジアでは保険料を支払えない人には公立病院で無償の医療が提供されますが、その内容は限定的です。本症例の患者さんも経済的な理由から医療保険を支払っていなかったため、MRIを撮影することができませんでした。執刀医は2年前に来日したDr. Puth Chendaでした。頚椎脱臼骨折を前方後方どちらから整復固定するかは術者や施設、国によって方針が異なると思われますが、本例では、まず病院にメイフィールドのピンが無く(紛失後に経済的な理由から補充できない)腹臥位で手術ができない、また患者さんが頚椎後方インプラントの費用を払えない、また頚椎前方の椎体間ケージの費用も払えない(カンボジアではケージ1個の方がプレート1枚とスクリュー4本より高額)、との理由から腸骨移植による前方手術しか選択肢はありませんでした。手術には湯川先生、青山先生が指導的助手として参加され、無事に完遂されました(図3)。Cambodia-China Friendship Preah Kossamak Hospitalは数年前に新病棟が建設され、手術室もとても綺麗でしたが(図4)、手術資材は不足しておりました。私たちは主に医学的視点から手術方針を決定しますが、病院と患者さんの経済状況から術式を決定しなければならないカンボジアの現実を目の当たりにしました。


二日目の3月7日はKhmer-Soviet Friendship Hospitalに戻り、The 8th Joint International Seminar and Workshop of Cervical Spine Surgeryが開催されました(プログラム別添)。午前中にセミナー、午後に手術手技ワークショップを行い、50名以上の現地の先生が参加されました (図5)。

Sim Sokchanカンボジア脳神経外科学会理事長、湯川先生、Ngy Meng病院長の挨拶の後、日本からの各医師が2演題ずつ、若手医師を対象として頚椎疾患・外傷の診断から手術までの合計6つの講演を行いました。積極的に多くの質問が寄せられ、明日からの診療に役立てたいというカンボジアの若い先生方の気持ちが伝わって気ました(図6)。特にinstrumentation手術に対する質問が多く、手術適応、手技、固定範囲などについて、充実したやり取りがなされました。日本からの講演の後は、カンボジア側から6名の先生方が登壇され、小児の歯突起骨折、成人の上位頚椎外傷、メッシュケージを使った前方固定術の治療経験などが発表されました。高度な環軸関節亜脱臼に対する後方固定術など、難易度が高い手術が当たり前のようにされており強く感銘を受けると同時に、病院間の医療資源の差、医師間の手術経験の差が大きいことも計り知れました。私たち日本人医師の訪問は、日本・カンボジア間の交流だけでなく、カンボジアの先生方が集まって互いの経験を共有する貴重な機会にもなると感じました。さらには、地元テレビ局が取材に訪れており、湯川先生が日本側を代表してインタビューに応じました(図7)。我々の取り組みが医師だけでなく、医療を通して地域にも貢献し得る活動であることを感じることができました。


午後からは模擬骨を用いたハンズオンセミナーを行いました。まず湯川先生から頚椎椎弓根スクリューおよび外側塊スクリューの挿入方法についてのレクチャーが全員に対して行われました(図8)。その後に3つの班に分かれ、それぞれ、(1)電動ドリルを用いた椎弓形成術および椎弓切除術、(2)環椎および軸椎に対するスクリュー挿入法、(3)頚椎前方除圧固定術、のワークショップを行いました。こちらも大変盛況で、各班で積極的な質問を多数いただきました。また、レクチャーと質疑のやりとりはビデオで撮影されており、大変充実したワークショップとなりました。

今回私はカンボジアとの交流事業に初めて現地参加させていただきました。やはり1日の手術支援、1日の講演で手術手技と知識を共有するだけでは限りがあります。現地の活動でだけでなく、事前にウェブミーティングを開催するなどして、現地手術症例の診断、治療計画決定に至るまでの思考過程、実際の手術手技の詳細などを事前に共有することができれば、現地2日間の活動がより大きな意味を持つようになるのではないかと思いました。カンボジアの先生方は年齢を問わず、皆当たり前のように英語でdiscussionします。さらに彼らは同様にフランス語にも堪能です。医学的側面からは我々がカンボジアの脊椎医療をサポートできることはまだまだ多いと感じる一方で、向上心に満ち溢れた若い先生方が生き生きと英語で質問をし、議論する様子を拝見し、むしろ日本が彼らの姿勢を学ぶべきではないかとも感じました。
最後になりますが、カンボジアとの交流事業をご支援いただき、この度の貴重な機会を頂戴いたしましことに清水敬親理事長、三原久範前事務局長、國府田正雄事務局長、アジア・パシフィック交流委員会の高畑雅彦委員長、委員の皆様に御礼申し上げます。また、JCSSの会員皆様、ご寄付を賜りました企業の皆様にもこの場を借りて御礼申し上げます。誠に有難うございました。
国際頚椎学会日本機構
アジア・パシフィック交流委員会委員
防衛医科大学校整形外科学講座
北村和也